ブログ
BLOG
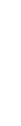
BLOG
まだまだ寒い日が続きますが、体調は大丈夫でしょうか?
昨年、今年とインフルエンザが流行りましたね・・・・・・
早速ですが、今年2回目のブログ更新をします。
今回のテーマは「骨折」です。
普段病院に行かない方でも、骨折という言葉は知れ渡っていますよね。ただこの骨折がどういう風に治るのか、その過程を知らない方は多いのではないでしょうか?
なので私の復習も含めて、知っていただきたいと思います。
骨折の種類
骨折は、骨が折れることを指しますが、その折れ方は様々です。全部挙げると大変なので代表的な骨折を紹介します。
①横骨折、②斜骨折、③螺旋骨折、④粉砕骨折、⑤圧迫骨折等があります。
そして折れた骨の名称に伴い、骨折名が決まります。手首の骨折の代表格である、橈骨遠位端骨折(図1:青丸で囲んでいる個所)は4大骨折とも言われており、当院でも治療する事が多い骨折です。
図1

固定するギプスも時期によって図2のような取り外しができるギプスもあり、固定する材料も発展しています。
図2

どのように治っていくのか?
まず治る仮定において「仮骨」の有無によって、骨癒合の過程が変わってきます。
仮骨が形成されず骨癒合をすることを一次性骨癒合といい、仮骨が形成されて骨癒合することを二次性骨癒合といいます。
もう少し、深堀をしていきましょう。そもそも仮骨がどのように形成されるのかといえば、炎症期(骨折直後~数日)、修復期(6~8週まで)、リモデリングor再造形期(数か月空数年)と治癒過程に分けられます(文献によって時期、名称は異なるので参考程度に見てください)。その中で修復期空~リモデリング期に仮骨が形成されます。
そもそも仮骨が形成されない状況は、①骨折部の断端が整復されている、②転移がない、③圧迫プレート等により強固に固定されていることが条件になります。
どっちの骨癒合がいいの?
これに関しては、医師が転移、骨折の形態、手術or保存等の条件を考え選択するので、医師の判断によって分かれると思います。
一次性骨癒合は骨癒合速度が遅く、二次性骨癒合は骨癒合速度が速いという特性があります。
医師と作業療法士の連携
今までは、骨が治る話を中心にしていましたが、骨が治ればそれで終わりではありません。骨が折れた経緯にもよりますが、骨が折れるぐらいの外力が加わった場合は、骨の周りにある組織も損傷している可能性があります。
その場合は、手首の動きが悪くなり、神経が圧迫され痺れが出現する可能性もあり、日常生活に支障がでます。
当院では、手を専門にする星野医師が在籍し、作業療法士としっかり連携をとりしっかり治療を行っています。
作業療法士として骨折の治療をしていくうえで、記載したような知識がなければ医師とコミュニケーションが取れないため、当院では手の治療は全て作業療法士が担い、研鑽をしております。
大分で骨折した方が、早く社会復帰できるように取り組み、ほしの整形に来て良かったと思われるように、これからも精進していきます。
文責:村上